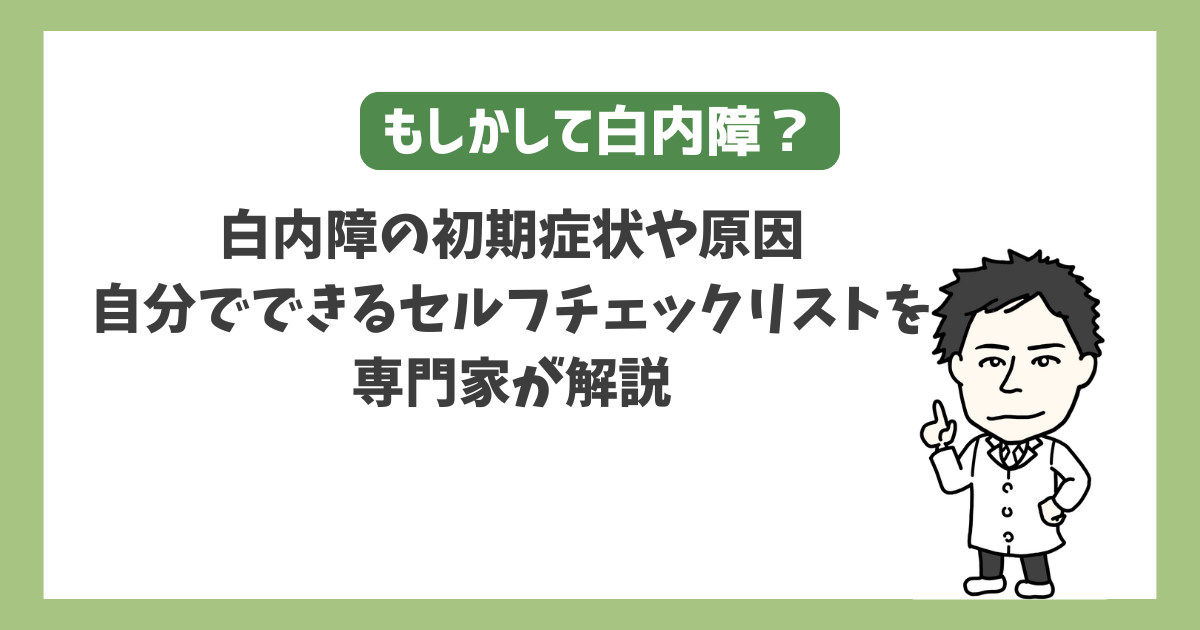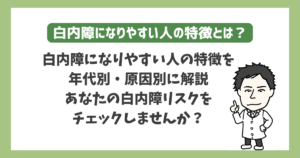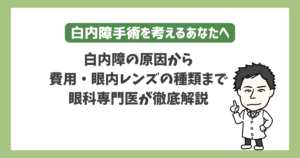「最近、なんとなく目が見えにくくなった」「車の運転中、対向車のライトがやけにまぶしく感じる」「メガネの度が合わなくなった気がする」
このような目の不調を感じて、「もしかして白内障かも?」と不安に思っている方はいませんか?
白内障は、特に中高年の方にとって非常に身近な目の病気です。実は、80歳を過ぎるとほとんどの人が白内障になっていると言われています。しかし、「年だから仕方ない」と放置してしまうと、視力がどんどん低下し、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
この記事では、白内障に関心のある方や、ご自身の症状に不安を感じている方に向けて、初期症状から原因、セルフチェック、最新治療法などを詳しく、そして分かりやすく解説していきます。
この記事を最後まで読めば、白内障に関する正しい知識が身につき、ご自身の目の状態を理解し、今後の適切な対応を考えるための一助となるはずです。目の健康を守るために、まずはご自身の状態を知ることから始めましょう。
白内障とは?目のレンズ「水晶体」が濁る病気
まず、白内障がどのような病気なのかを理解しましょう。私たちの目の中には、「水晶体(すいしょうたい)」と呼ばれる組織があります。これは、カメラのレンズのような役割を果たしており、外から入ってきた光を集めてピントを合わせ、網膜(フィルムの役割)に像を映し出すための、透明な凸レンズ状の組織です。
正常な水晶体は透明で、光をスムーズに通します。しかし、何らかの原因でこの水晶体の主成分であるタンパク質が変性し、白く濁ってしまうことがあります。この状態が「白内障」です。
水晶体が濁ると、光がうまく通過できなくなったり、光が乱反射したりします。その結果、すりガラスを通して物を見ているように、視界がかすんだり、ぼやけて見えたりするのです。一度濁ってしまった水晶体は、残念ながら薬で元の透明な状態に戻すことはできません。
白内障は主に加齢が原因で起こることが多く、一種の老化現象とも言えます。そのため、白髪が増えたり、肌にしわができたりするのと同じように、誰にでも起こりうる病気なのです。日本における失明原因の第1位は緑内障ですが、かつては白内障が最多でした。現在では手術技術が飛躍的に進歩したため、適切な治療を受ければ視力を取り戻せる病気になっています。
もしかして白内障?今すぐできる症状セルフチェックリスト
「白内障かもしれない」と感じたら、まずはご自身の症状を客観的にチェックしてみましょう。以下に挙げる項目に複数当てはまる場合は、白内障の可能性があります。ただし、これはあくまで目安です。正確な診断のためには、必ず眼科を受診してください。
【白内障の初期症状セルフチェック】
- 全体的に目がかすむ、霧がかかったように見える
最も多くの患者さんが自覚する症状です。すりガラス越しに見ているような、ぼんやりとした見え方になります。 - 視力が低下してきた
メガネやコンタクトレンズを新しくしても、視力が思うように矯正できなくなります。 - 光をまぶしく感じる(羞明:しゅうめい)
太陽光や室内灯、特に夜間の対向車のヘッドライトなどを以前より強くまぶしく感じるようになります。 - 光の周りに虹のような輪が見える(ハロー現象)
電灯などの光の周りに、虹色の輪がかかって見えることがあります。 - 物が二重、三重に見える(単眼複視)
片目だけで見ても、物がダブって見えることがあります。乱視とは異なる見え方です。 - 暗い場所や夜間になると、特によく見えない
明るい場所と暗い場所で見え方の差が激しくなり、特に夜間の外出や運転が怖く感じることがあります。 - 色の区別がつきにくくなった
水晶体の濁りが黄色味を帯びてくるため、全体的に黄色がかった視界になり、青色などの識別が難しくなることがあります。 - 一時的に近くが見やすくなった
白内障の進行過程で水晶体の屈折力が変化し、一時的に老眼が改善されたように感じることがあります。しかし、これは症状が進行しているサインです。
これらの症状は、ゆっくりと進行するため、ご自身では気づきにくいことも少なくありません。少しでも気になることがあれば、早めに専門医に相談することが大切です。
白内障の主な原因は「加齢」だけではありません
白内障の最も一般的な原因は「加齢」ですが、それ以外にもさまざまな要因で発症することがあります。若いからといって安心はできません。
加齢性白内障
最も多いタイプで、全体の9割以上を占めます。原因は完全には解明されていませんが、長年にわたって浴び続ける紫外線や、体内の酸化ストレスなどが水晶体のタンパク質を変性させると考えられています。早い人では40代から発症し、50代で約半数、60代で7〜8割、80代以上ではほとんどの人に白内障による水晶体の濁りが見られます。
若年性白内障
比較的若い世代(40歳未満)で発症する白内障を総称して「若年性白内障」と呼びます。以下のような原因が挙げられます。
- アトピー性皮膚炎:顔、特に目の周りを強くこすったり、叩いたりする物理的な刺激が原因となることがあります。
- 糖尿病:高血糖の状態が続くと、水晶体の中にソルビトールという物質が溜まり、水晶体の浸透圧が変化して濁りを生じさせます。血糖コントロールが非常に重要です。
- ステロイド薬の長期使用:他の病気の治療のために、ステロイド薬(内服薬、点眼薬、吸入薬、塗り薬など)を長期間使用している場合に、副作用として発症することがあります。
- 目の外傷:ボールが目に当たるなどの強い衝撃(打撲)や、目に何かが刺さるなどの怪我によって水晶体が傷つき、白内障を引き起こすことがあります。
- その他の目の病気:ぶどう膜炎など、目の中の炎症が原因となることがあります。
- 放射線・紫外線:放射線治療や、長期間にわたって強い紫外線を浴び続けることもリスク因子です。
- 先天性白内障:生まれつき水晶体が濁っている状態で、風疹の母子感染などが原因となることがあります。
見え方の違いは?「老眼」と「白内障」
40代以降になると多くの人が経験する「老眼(老視)」。手元が見えにくくなるという点で、白内障と混同されがちですが、これらは全く異なるメカニズムで起こります。
| 老眼 | 白内障 | |
|---|---|---|
| 原因 | 水晶体の弾力性が失われ、ピント調節機能が衰えること。 | 水晶体のタンパク質が変性し、濁ってしまうこと。 |
| 主な症状 | ・手元や近くの文字が見えにくい ・ピントが合いにくい ・薄暗いとさらに見えにくい | ・全体的にかすむ、ぼやける ・光がまぶしい ・物が二重に見える ・視力そのものが低下する |
| 対処法 | 老眼鏡(リーディンググラス)や遠近両用コンタクトレンズで矯正する。 | 進行を遅らせる点眼薬、根本治療は手術が必要。メガネでは矯正しきれない。 |
簡単に言うと、老眼は「ピント調節の問題」、白内障は「レンズの透明度の問題」です。老眼は、近くを見るときにピントが合わないだけで、遠くは問題なく見えますし、視界のかすみやまぶしさはありません。一方、白内障は視界全体が影響を受けます。ただし、両方が同時に進行することもありますので、自己判断は禁物です。
白内障の検査と診断の流れ
眼科では、白内障の有無や進行度、また他の目の病気が隠れていないかを調べるために、いくつかの検査を行います。いずれも痛みはなく、短時間で終わる検査ですので、安心して受診してください。
- 視力検査:矯正視力(メガネやコンタクトで最もよく見える視力)を測定します。白内障が進行すると、矯正しても良い視力が出なくなります。
- 細隙灯顕微鏡検査(さいげきとうけんびきょうけんさ):細い光を目に当てて、顕微鏡で水晶体の濁りの有無、程度、位置を詳細に観察します。白内障の確定診断に不可欠な検査です。
- 眼圧検査:眼球の硬さ(眼圧)を測定します。緑内障など、他の病気がないかを調べるために行います。
- 眼底検査:瞳孔を開く目薬をさした後、網膜や視神経の状態を調べます。加齢黄斑変性や糖尿病網膜症など、視力低下を引き起こす他の病気がないかを確認するために非常に重要です。
これらの検査結果を総合的に判断し、医師が白内障の診断と進行度を判定します。
白内障の治療法|進行度に合わせて選択
白内障の治療は、大きく分けて「薬物療法」と「手術療法」の2つがあります。進行度や、日常生活にどれくらい支障が出ているかに応じて治療方針が決定されます。
初期段階:点眼薬による進行予防
白内障がまだ初期で、視力も比較的良好であり、日常生活に大きな不便を感じていない場合は、進行を遅らせることを目的とした点眼薬による治療が選択されることがあります。
代表的な薬には、ピレノキシン製剤やグルタチオン製剤などがあります。これらは、水晶体のタンパク質が変性するのを抑制する効果が期待されています。
ただし、ここで非常に重要なことは、これらの点眼薬はあくまで「進行を緩やかにする」ためのものであり、「濁った水晶体を透明に戻す」効果や「低下した視力を回復させる」効果はないということです。白内障を根本的に治すには、手術が必要となります。
進行した場合:手術による根本治療
白内障が進行し、「かすみが強くて仕事に集中できない」「まぶしくて運転が怖い」「趣味の裁縫が楽しめない」など、日常生活に不便を感じるようになったら、手術が検討されます。白内障手術は、現在行われている外科手術の中で最も件数が多い手術の一つであり、安全性と有効性が確立されています。
【手術のタイミング】
昔は「よく見えるようになるまで待つ」と言われたこともありましたが、現在では、患者さん自身が「不便だ」と感じた時が最適な手術のタイミングとされています。運転免許の更新で視力基準を満たせなくなったことをきっかけに手術を決意される方も多くいます。
【一般的な手術方法:超音波水晶体乳化吸引術】
現在、主流となっている手術方法は「超音波水晶体乳化吸引術」です。
- 目の局所麻酔(点眼麻酔が主流)を行います。
- 角膜(黒目)の縁を2~3mmほど小さく切開します。
- その小さな切開創から超音波を出す器具を挿入し、濁った水晶体を細かく砕きながら吸引して取り除きます。この時、水晶体を包んでいる「水晶体嚢(のう)」という袋は残しておきます。
- 残した水晶体嚢の中に、人工のレンズである「眼内レンズ」を挿入します。
手術時間は通常10分~20分程度で、多くの場合、入院の必要がない日帰り手術が可能です。
手術の満足度を左右する「眼内レンズ」の種類と選び方
白内障手術では、濁った水晶体の代わりとなる「眼内レンズ」を目の中に挿入します。この眼内レンズは、一度挿入すると特別なことがない限り交換はしません。そのため、どのレンズを選ぶかが、手術後の見え方や生活の質(QOL)を大きく左右する非常に重要な選択となります。
眼内レンズは、ピントが合う距離によって大きく「単焦点眼内レンズ」と「多焦点眼内レンズ」に分けられます。
単焦点眼内レンズ(保険適用)
- 特徴:遠く・中間・近くのいずれか1つの距離にだけピントが合うレンズです。
- メリット:
- 健康保険が適用されるため、費用負担が少ない。
- レンズの構造がシンプルなため、光のロスが少なく、コントラスト(色の濃淡や輪郭)がはっきりとした質の高い見え方が期待できる。
- ハロー・グレア(光のにじみやまぶしさ)が少ない。
- デメリット:
- ピントを合わせた距離以外はぼやけて見えるため、生活の多くの場面でメガネ(老眼鏡や中間距離用のメガネ)が必要になります。例えば、遠くにピントを合わせた場合は、車の運転は裸眼でできますが、手元のスマートフォンや本を読むときには老眼鏡が必要です。
- おすすめの人:
- 手術後もメガネをかけることに抵抗がない方。
- 夜間に運転する機会が多い方。
- 色のコントラストが重要な仕事や趣味(写真、デザインなど)をお持ちの方。
- 手術費用を抑えたい方。
多焦点眼内レンズ(選定療養または自由診療)
- 特徴:遠くと近く(2焦点)、あるいは遠く・中間・近く(3焦点)など、複数の距離にピントが合うように設計されたレンズです。
- メリット:
- メガネを使う頻度を大幅に減らすことができ、裸眼で生活できる時間が増えます。老眼も同時に解消できるイメージです。
- スポーツや旅行、料理など、さまざまな場面でメガネの煩わしさから解放されます。
- デメリット:
- 選定療養や自由診療となるため、費用が高額になります。(※選定療養:追加費用を自己負担することで保険適用の治療と併用できる制度)
- レンズの構造上、光が複数の焦点に振り分けられるため、単焦点レンズに比べてコントラストがやや低下したり、暗い場所で見えにくいと感じたりすることがあります。
- 夜間に光がにじんだり、まぶしく見えたりするハロー・グレアを感じやすい傾向があります。(最近のレンズではかなり改善されています)
- おすすめの人:
- 手術後はできるだけメガネなしで生活したい方。
- 仕事や趣味で、さまざまな距離を頻繁に見る必要がある方。
- 老眼も一緒に治したいと考えている方。
- 費用よりも、生活の利便性を重視したい方。
どちらのレンズが優れているということではなく、それぞれに長所と短所があります。ご自身のライフスタイル(仕事、趣味、運転の有無など)や、手術後の見え方に対する希望を具体的に医師に伝え、よく相談して最適なレンズを選ぶことが、手術の満足度を高める上で最も重要です。
白内障手術の流れと費用の目安
手術決定から術後までの流れ
- 術前検査:手術日を決定したら、眼内レンズの度数を決めるための精密検査(眼軸長測定など)や、全身状態を確認するための血液検査などを行います。
- 手術当日:指定された時間に来院し、手術前の準備(散瞳薬の点眼など)をします。手術自体は10~20分程度で終了します。術後は、しばらく安静にした後、問題がなければ保護用のメガネをかけて帰宅できます。
- 術後検診:手術の翌日、3日後、1週間後、1ヶ月後…というように、定期的に検診を受けて、目の状態(感染症や炎症の有無など)をチェックします。医師の指示に従って、抗菌薬や抗炎症薬の点眼を一定期間続けることが非常に重要です。
費用の目安
白内障手術の費用は、選択する眼内レンズや医療機関によって異なります。
- 単焦点眼内レンズ(保険適用)の場合:
- 1割負担:約15,000円~20,000円(片眼)
- 2割負担:約30,000円~40,000円(片眼)
- 3割負担:約45,000円~60,000円(片眼)
- 多焦点眼内レンズ(選定療養)の場合:
上記保険適用の手術費用に加えて、レンズ代などの追加費用(自己負担分)がかかります。追加費用は、レンズの種類により異なりますが、片眼で15万円~40万円程度が目安です。
※上記はあくまで目安です。詳細は各医療機関にご確認ください。
また、医療費が高額になった場合は、「高額療養費制度」を利用することで、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。ご自身の加入している健康保険組合や市町村の窓口に問い合わせてみましょう。
白内障の進行を遅らせるために日常生活でできること
加齢による白内障を完全に予防することは困難ですが、その進行を遅らせるために、日々の生活の中で意識できることがあります。
- 紫外線対策を徹底する
水晶体にダメージを与える紫外線を防ぐことは、最も効果的な予防策の一つです。外出時には、UVカット機能のあるサングラスやつばの広い帽子を着用する習慣をつけましょう。 - 禁煙する
喫煙は体内の酸化ストレスを増大させ、白内障のリスクを高めることが知られています。目の健康のためにも、禁煙を心がけましょう。 - バランスの取れた食事
抗酸化作用のあるビタミンC、ビタミンE、ルテインなどを多く含む緑黄色野菜(ほうれん草、ブロッコリー、パプリカなど)や果物を積極的に摂取しましょう。 - 生活習慣病の管理
糖尿病は白内障の大きなリスク因子です。血糖値のコントロールを良好に保つことが、糖尿病性白内障の予防・進行抑制につながります。
まとめ:目の不調を感じたら、まずは眼科へ相談を
今回は、白内障の症状から原因、治療法までを詳しく解説しました。
白内障は加齢とともに誰にでも起こりうる病気ですが、決して「年のせい」と諦める必要はありません。適切な時期に適切な治療(手術)を受けることで、クリアな視界を取り戻し、生活の質を大きく向上させることができます。
特に、白内障手術における眼内レンズの選択は、その後の人生の見え方を決める重要な決断です。ご自身の生活スタイルに合ったレンズを選ぶためにも、信頼できる医師と十分に話し合うことが大切です。
「最近、見え方がおかしいな」と感じたら、それはあなたの目が送っているサインかもしれません。自己判断で放置せず、まずは一度、お近くの眼科専門医を受診し、ご自身の目の状態を正確に把握することから始めてください。早期発見・早期対応が、あなたの目の健康を守るための第一歩です。