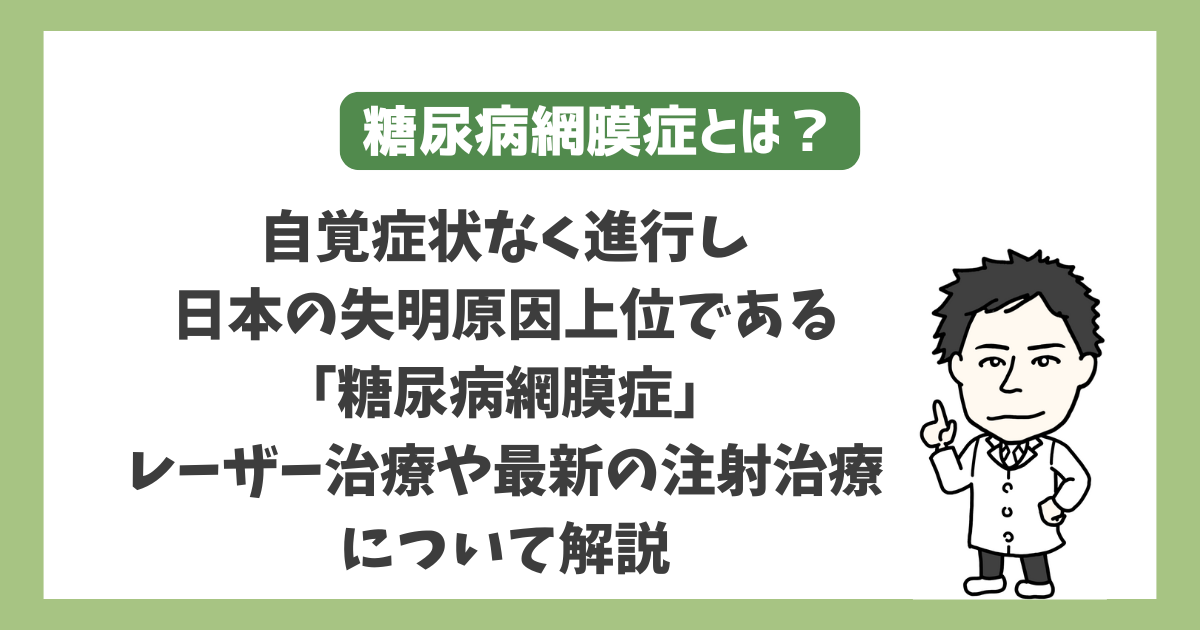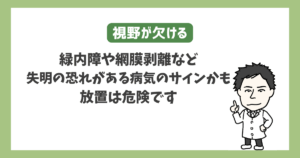「健康診断で糖尿病と診断された」
「血糖値が高いと指摘された」
そのような方が、内科の先生から「眼科にも行ってくださいね」と言われて、なぜだろう?と思われたことはありませんか?
糖尿病は、全身の血管に影響を及ぼす病気です。特に、目には非常に細い血管が網の目のように張り巡らされているため、高血糖によるダメージを受けやすく、様々な目の病気を引き起こす可能性があります。中でも「糖尿病網膜症」は、日本の成人における失明原因の上位を占める、非常に怖い病気です。
しかし、怖い病気ではありますが、適切な時期に適切な治療を受ければ、失明という最悪の事態を防ぐことは十分に可能です。そのために最も重要なのが「眼科の定期検診」です。
この記事では、なぜ糖尿病が目に悪いのか、代表的な目の合併症「糖尿病網膜症」の進行と症状、眼科で行われる検査や治療法、定期検診がいかに大切かなどについて、詳しく、そして分かりやすく解説していきます。
ご自身の、あるいは大切なご家族の「見える未来」を守るために、ぜひ最後までお読みください。
糖尿病が目に影響を及ぼす「なぜ?」高血糖と血管の関係
そもそも、なぜ糖尿病が目に影響を与えるのでしょうか。その鍵を握っているのが「高血糖」と「血管」です。
糖尿病は、インスリンというホルモンの働きが悪くなることで、血液中のブドウ糖(血糖)が過剰になる状態(高血糖)が続く病気です。この高血糖の状態が長く続くと、全身の血管、特に細い血管(細小血管)の壁が傷つき、もろくなってしまいます。
血管は、体中に酸素や栄養を運ぶ大切な役割を担っています。その血管が傷つくと、血液の流れが悪くなったり、血管が詰まったり、血液の成分が漏れ出したりといったトラブルが起こります。これが「糖尿病の合併症」の正体です。
そして、私たちの目、特に「網膜」というカメラのフィルムにあたる部分には、栄養を供給するための非常に細い血管がびっしりと張り巡らされています。そのため、糖尿病による高血糖の影響を真っ先に、そして非常に受けやすい場所なのです。
高血糖によって網膜の血管がダメージを受けることで、「糖尿病網膜症」をはじめとする様々な目の病気が引き起こされてしまうのです。
糖尿病の三大合併症の一つ「糖尿病網膜症」とは?
糖尿病の合併症の中でも、特に深刻なものとして「三大合併症」と呼ばれるものがあります。「糖尿病神経障害」「糖尿病腎症」、そして今回詳しく解説する「糖尿病網膜症」です。糖尿病網膜症は、日本の失明原因として常に上位に挙げられており、決して軽視できない病気です。
自覚症状がないまま進行する「沈黙の病気」
糖尿病網膜症の最も怖い点は、「初期から中期にかけて、ほとんど自覚症状がない」ということです。
血糖値が高い状態が続いていても、目の見え方に変化を感じることはほとんどありません。そのため、「まだ見えているから大丈夫」と自己判断し、眼科を受診しないまま放置してしまう患者さんが少なくありません。そして、かすみ目や視力低下といった症状を自覚した時には、病気はかなり進行してしまっており、治療が困難になるケースも多いのです。
この「静かに進行する」という特徴から、糖尿病網膜症はまさに“サイレントキラー”と呼べる病気です。だからこそ、症状がないうちから定期的に眼科で検査を受けることが、何よりも重要になります。
糖尿病網膜症の3つの進行ステージと症状
糖尿病網膜症は、進行の度合いによって大きく3つのステージに分けられます。それぞれの段階で網膜にどのような変化が起きるのかを見ていきましょう。
ステージ1:単純糖尿病網膜症(初期)
【網膜の状態】
高血糖により、網膜の細い血管がもろくなり始めます。血管の壁に小さなこぶ(毛細血管瘤)ができたり、血液中のたんぱく質や脂肪が漏れ出してシミ(硬性白斑)を作ったり、小さな出血(点状・斑状出血)が見られたりします。
【自覚症状】
この段階では、自覚症状はほとんどありません。視力も正常なことが多いため、患者さん自身が目の異常に気づくことはまず不可能です。しかし、水面下では着実に病気が進行しています。この段階で発見し、血糖コントロールを徹底することが非常に重要です。治療の基本は、内科での血糖コントロールになります。
ステージ2:増殖前糖尿病網膜症(中期)
【網膜の状態】
血管のダメージがさらに進み、血流が悪い部分(虚血)が広がってきます。すると、網膜は「酸素が足りない!」という危険信号を発信します。血管が詰まり、神経線維がむくんで白いシミ(軟性白斑)ができたり、血管の形が不規則になったりします。網膜の血流不足が広範囲に及ぶと、次の危険なステージである「増殖網膜症」へと移行してしまいます。
【自覚症状】
この段階でも、まだ自覚症状がないことが多いですが、人によっては、目のかすみなどを感じることがあります。眼科では、血流不足が広がっている部分に「網膜光凝固術(レーザー治療)」を行い、病気の進行を食い止める治療が検討され始めます。
ステージ3:増殖糖尿病網膜症(末期)
【網膜の状態】
血流不足が深刻になった網膜では、酸素を補おうとして「新生血管」という、もろくて破れやすい異常な血管が生まれてきます。この新生血管は、網膜や、その手前にある硝子体というゲル状の組織に向かって伸びていきます。新生血管は非常にもろいため、簡単に大出血(硝子体出血)を起こします。
さらに、新生血管とともに増殖膜という膜が網膜の上に張ってしまい、これが網膜を引っ張ることで「牽引性網膜剥離」を引き起こすこともあります。また、新生血管が隅角という眼内の水の出口を塞いでしまうと、眼圧が急上昇する「血管新生緑内障」という治療が非常に難しい緑内障を発症します。
【自覚症状】
このステージになると、はっきりとした自覚症状が現れます。
- 飛蚊症(ひぶんしょう):目の前に蚊やゴミのようなものが飛んで見える。硝子体出血の初期症状のことがあります。
- 急激な視力低下:硝子体出血が大量に起こると、目の前が真っ暗になり、ほとんど見えなくなります。
- 視野欠損、歪み:網膜剥離が起こると、視野の一部が欠けたり、物が歪んで見えたりします。
ここまで進行すると、レーザー治療だけでは対応できず、「硝子体手術」という大掛かりな手術が必要になります。手術をしても、元の視力まで回復することは難しく、失明に至る危険性が非常に高くなります。
網膜症だけじゃない!糖尿病が引き起こす目の病気
糖尿病が原因で起こる目の病気は、網膜症だけではありません。以下のような病気も、糖尿病の患者さんは発症しやすくなるため注意が必要です。
- 白内障:目の中でレンズの役割をしている水晶体が濁る病気です。加齢とともに誰にでも起こり得ますが、糖尿病の患者さんは比較的若い年齢で発症しやすく、進行も早い傾向があります。
- 血管新生緑内障:増殖糖尿病網膜症が原因で起こる、非常に治療が難しい緑内障です。急激な眼圧上昇により、激しい目の痛みや頭痛、吐き気を伴うこともあり、急速に視神経がダメージを受けて失明に至る危険性が高い病気です。
- 目の神経の麻痺:高血糖により、目を動かす神経(動眼神経など)が麻痺することがあります。これにより、物が二重に見える「複視」や、まぶたが下がってしまう「眼瞼下垂」といった症状が突然現れることがあります。
眼科ではどんな検査をするの?
「眼科の検査」と聞くと、少し不安に思う方もいるかもしれません。しかし、いずれも目の状態を正確に把握し、あなたの視力を守るために不可欠な検査です。主に以下のような検査が行われます。
- 視力検査:見え方の基本をチェックします。糖尿病網膜症の進行度を判断する上での大切な指標です。
- 眼圧検査:眼球の硬さを測定します。特に、血管新生緑内障の発見に重要です。
- 眼底検査(散瞳検査):糖尿病網膜症の検査で最も重要なのが、この眼底検査です。点眼薬で瞳孔を大きく開かせ(散瞳)、網膜の血管の状態を隅々まで詳しく観察します。出血や白斑、新生血管の有無などを直接確認できます。
【注意点】散瞳すると、4~5時間は光がまぶしく感じたり、ピントが合いにくくなったりします。そのため、検査当日はご自身での車やバイク、自転車の運転は絶対にできません。公共交通機関を利用するか、ご家族に送迎を頼むようにしてください。 - 光干渉断層計(OCT)検査:網膜の断面を撮影し、むくみ(黄斑浮腫)の有無や程度を詳細に調べることができる検査です。被ばくもなく、短時間で終わります。
- 蛍光眼底造影検査:腕の血管から造影剤を注入し、眼底カメラで網膜の血流状態を撮影する検査です。血管が詰まっている場所や、血液が漏れている場所を正確に特定でき、レーザー治療の方針決定などに役立ちます。
糖尿病網膜症の治療法について
もし糖尿病網膜症が見つかった場合、どのような治療が行われるのでしょうか。治療の基本から、進行度に応じた眼科的治療までを解説します。
すべての基本は「良好な血糖コントロール」
まず、どんなステージであっても、最も重要で、すべての治療の土台となるのが「血糖コントロール」です。内科の主治医の指導のもと、食事療法、運動療法、そして必要であれば薬物療法を行い、血糖値を安定させることが、網膜症の進行を抑える上で不可欠です。
眼科での治療をいくら行っても、血糖コントロールが悪いままでは、いたちごっこになってしまいます。内科と眼科が連携し、車の両輪のように治療を進めていくことが大切です。
進行度に応じた眼科的治療
血糖コントロールを基本としながら、網膜症の進行度に応じて以下のような眼科的治療が行われます。
レーザー光凝固術
増殖前網膜症や、増殖網膜症の一部に対して行われる治療法です。血流が悪くなった網膜にレーザーを照射し、新生血管が発生するのを予防したり、すでにある新生血管を焼き固めて活動を抑えたりします。病気の進行を食い止めることが目的であり、失われた視力を回復させる治療ではありません。
抗VEGF薬硝子体内注射
新生血管の発生や、網膜のむくみ(黄斑浮腫)の原因となるVEGF(血管内皮増殖因子)という物質の働きを抑える薬を目の中に直接注射する治療法です。近年、非常に効果的な治療法として広く行われています。新生血管を退縮させたり、黄斑浮腫を改善させて視力を向上させる効果が期待できますが、効果は一時的なため、複数回の注射が必要になることが一般的です。
硝子体手術
増殖網膜症が進行し、硝子体出血や牽引性網膜剥離が起こってしまった場合に行われる手術です。目の中に細い器具を入れ、出血や増殖膜を取り除き、剥がれた網膜を元に戻します。これは視力を維持するための最後の砦ともいえる治療法ですが、手術をしても視機能が完全には元に戻らないことも少なくありません。
まとめ:定期的な眼科受診が、あなたの「見える未来」を守ります
ここまで、糖尿病と目の関係、特に糖尿病網膜症について詳しく解説してきました。最後に、この記事で最もお伝えしたい大切なことを繰り返します。
糖尿病網膜症は、初期には全く自覚症状がありません。
しかし、症状がないうちから、あなたの目の中では病気が静かに進行している可能性があります。
そして、見え方に異常を感じた時には、すでに手遅れに近い状態まで進行しているかもしれないのです。
この怖い病気からあなたの目を守る、最も確実で、唯一の方法。それが「症状がなくても、定期的に眼科を受診すること」です。
糖尿病と診断されたら、まずは一度、必ず眼科を受診してください。そこで異常がなくても、内科の主治医と眼科医の指示に従い、少なくとも年に1回は定期検診を受けましょう。もし網膜症が始まっていたとしても、初期の段階で発見できれば、血糖コントロールの改善と適切な治療で、良好な視力を生涯にわたって維持できる可能性は格段に高まります。
「まだ見えるから大丈夫」「忙しいからまた今度」という油断が、かけがえのない視力を奪うきっかけになりかねません。糖尿病は、自己管理が非常に重要な病気です。日々の血糖コントロールに加えて、定期的な眼科受診も、あなた自身の大切な健康管理の一環です。
この記事を読んで、少しでも眼科受診の重要性を感じていただけたなら幸いです。ぜひ、かかりつけの眼科を見つけ、予約の電話をするところから始めてみてください。その一歩が、あなたの10年後、20年後の「見える」を守るための、最も重要な一歩となるはずです。