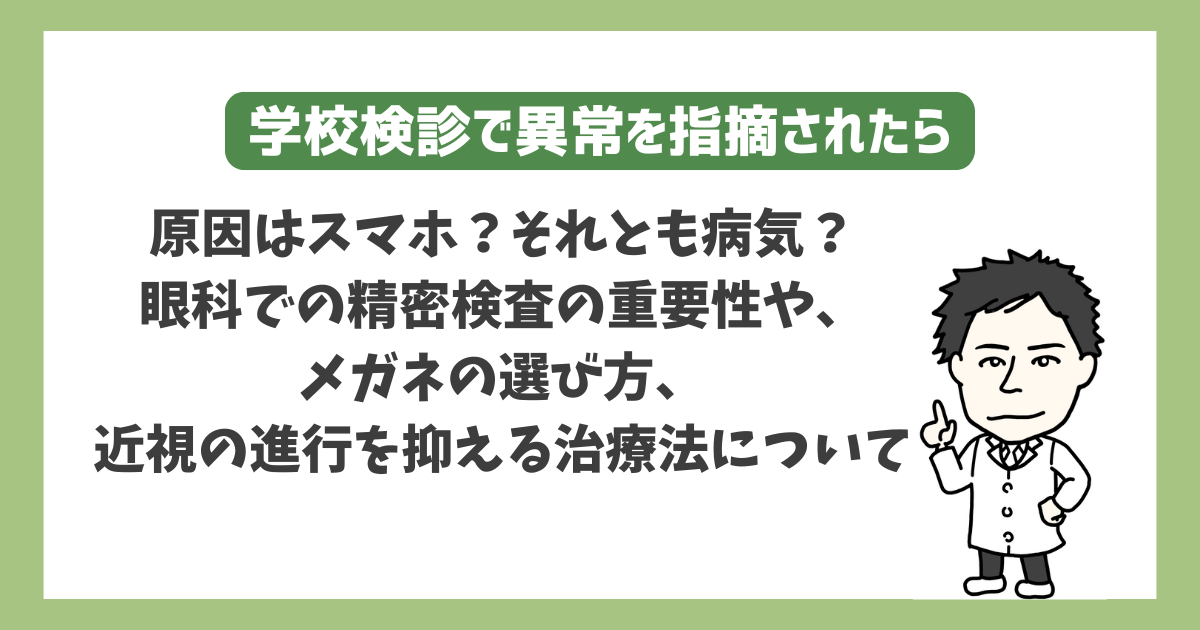春や秋に行われる学校の健康診断。その中でも、保護者の方が特に気になる項目の一つが「視力検査」ではないでしょうか。ある日、お子さんが学校から「眼科受診のおすすめ」というプリントをもらってきたら、「うちの子の目が悪くなったの?」「スマホやゲームのさせすぎ?」「このまま視力が下がり続けたらどうしよう…」と、様々な不安が頭をよぎるかもしれません。
ご安心ください。学校検診での視力低下の指摘は、お子さんの目の状態を正確に知り、適切な対策を始めるための大切なサインです。決して「様子を見よう」と自己判断せず、まずは専門家である眼科医に相談することが何よりも重要です。
この記事では、学校検診で視力低下を指摘された保護者の方に向けて、以下の内容を詳しく解説します。
- 学校の視力検査(A・B・C・D)の評価の意味
- お子さんの視力が低下する主な原因
- 眼科で行う精密検査の内容
- 視力低下に対する具体的な対策と専門的な治療法
- 大阪市鶴見区・城東区で信頼できる眼科の選び方
この記事を最後までお読みいただくことで、視力低下への不安が解消され、お子さんの目の健康を守るために今すべきことが明確になります。そして、大阪市鶴見区・城東区やその周辺にお住まいの皆さまが、安心して相談できる「大阪鶴見まつやま眼科」についてご紹介します。
学校の視力検査、A・B・C・D判定の意味を正しく知ろう
まず、学校検診の結果について正しく理解することから始めましょう。学校での視力検査は、あくまでスクリーニング(ふるい分け)検査であり、確定診断ではありません。教室や保健室など、必ずしも最適な環境とは言えない場所で行われるため、正確な視力を測るための第一段階と捉えてください。
視力は以下のように判定されます。
- A判定(視力1.0以上):教室の一番後ろの席でも黒板の文字がはっきり見える視力です。現時点では問題ありません。
- B判定(視力0.9~0.7):教室の真ん中より後ろの席だと、小さい文字が見えにくくなることがある視力です。まだ日常生活に大きな支障はないかもしれませんが、近視が始まっている可能性があります。眼科での精密検査が推奨されます。
- C判定(視力0.6~0.3):教室の真ん中より前の席に座らないと黒板の文字が見えにくい視力です。明らかに視力が低下しており、日常生活にも影響が出ている可能性があります。早急な眼科受診が必要です。
- D判定(視力0.2以下):教室の一番前の席に座っても黒板の文字が見えにくい視力です。メガネなどによる視力矯正がすぐに必要です。必ず眼科を受診してください。
特に「B判定」は注意が必要です。「まだ見えているから大丈夫」と放置してしまうと、気づかないうちに近視が進行してしまうケースが少なくありません。「B判定」でも、お子さんが目を細める、首を傾けて物を見る、集中力がないといった様子が見られる場合は、視力低下が原因かもしれません。「B判定」以上、つまりB・C・D判定を受け取った場合は、必ず眼科を受診しましょう。
なぜ?子供の視力が低下する3つの主な原因
「どうしてうちの子の視力が下がってしまったのだろう?」と原因が気になる保護者の方は多いでしょう。お子さんの視力低下は、主に以下の3つの要因が複雑に絡み合って起こると考えられています。
1. 環境要因:スマホ・タブレット・ゲームとの付き合い方
現代の子供たちを取り巻く環境は、昔に比べて格段に近くを見る時間(近業)が増えています。これが視力低下、特に近視の最も大きな原因とされています。
- 近業の増加:スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機、パソコン、読書、勉強など、30cm以内の近い距離を長時間見続ける作業は、目のピントを合わせる筋肉(毛様体筋)を緊張させ続けます。この緊張が続くと、筋肉が凝り固まってしまい、遠くを見たときにピントが合いにくくなる「仮性近視」や、眼球の長さ(眼軸長)が伸びてしまう「軸性近視」につながります。
- 屋外活動の減少:一方で、外で遊ぶ時間が減ったことも近視の進行に関係があると言われています。太陽光に含まれるバイオレットライトには、近視の進行を抑制する効果があるという研究報告があります。屋外で遠くの景色を見る機会が減り、室内での近業時間が増えるという現代のライフスタイルが、子供たちの視力に影響を与えているのです。
2. 遺伝的要因:ご両親の視力は関係する?
「親が近視だと子供も近視になりやすい」という話を聞いたことがあるかもしれません。実際に、ご両親ともに近視の場合、お子さんが近視になる確率は高くなるというデータがあり、遺伝的な要因も無視できません。ただし、遺伝だけで全てが決まるわけではありません。遺伝的な素因があったとしても、後述する生活習慣の改善や適切な治療によって、近視の進行を緩やかにすることは可能です。
3. 病気の可能性:単なる近視ではない場合も
学校検診で指摘される視力低下の多くは「近視」ですが、中には他の目の病気が隠れている可能性もあります。自己判断で「近視だろう」と決めつけるのは危険です。
- 遠視:遠視は「遠くが良く見える目」と思われがちですが、実は常にピントを合わせる努力をしないと、遠くも近くもぼやけて見える状態です。特に子供はピントを合わせる力が強いため、軽い遠視は見逃されがちです。しかし、常に目に負担がかかっているため、疲れやすい、集中力がない、頭痛を訴えるなどの症状が出ることがあります。強い遠視を放置すると、視力の発達が妨げられる「弱視」や、斜視の原因になることもあります。
- 乱視:角膜や水晶体の歪みによって、ピントが一点に合わず、物が二重に見えたり、ぼやけて見えたりする状態です。乱視が強いと、見えにくさから目を細める癖がついたり、疲れ目の原因になったりします。
- 弱視:メガネやコンタクトレンズで矯正しても、視力が1.0まで出ない状態を「弱視」といいます。視力の発達期(おおむね8歳頃まで)に、強い遠視や乱視、斜視などがあり、網膜に鮮明な像が映らない状態が続くことで、脳に正しく映像を伝える能力が育たないために起こります。弱視は早期発見・早期治療が非常に重要で、治療開始が遅れると、生涯にわたって視力が改善しない可能性があります。
これらの病気は、眼科での精密検査を受けなければ正確に診断できません。だからこそ、学校検診で視力低下を指摘されたら、まずは眼科を受診することが大切なのです。
眼科ではどんな検査をするの?学校検診との違い
「眼科に行っても、また同じ視力検査をするだけじゃないの?」と思われるかもしれませんが、全く違います。眼科では、お子さんの目の状態を正確に把握するための、専門的な精密検査を行います。
- 視力検査:学校で行うランドルト環(Cのマーク)を使った検査に加え、メガネやコンタクトレンズを使った場合の「矯正視力」を測定します。どこまで視力が出るのかを確認する重要な検査です。
- 屈折検査:専用の機械(オートレフケラトメーター)を使い、近視・遠視・乱視がどの程度あるのかを客観的に測定します。
- 調節麻痺下屈折検査(サイプレジン検査):お子さんの正確な視力を知るために最も重要な検査です。子供の目はピントを合わせる力(調節力)が非常に強いため、普段の検査では本来よりも近視が強く出たり、隠れた遠視が見逃されたりすることがあります。そこで、目の緊張をほぐす目薬(調節麻痺薬)を使って、目の本来の屈折状態(本当の近視や遠視の度数)を正確に測定します。この検査をすることで、「仮性近視」なのか、本当に治療が必要な「真性近視」なのかを正しく診断できます。
- 眼軸長(がんじくちょう)検査:眼球の奥行きの長さを測定する検査です。近視の多くは、この眼軸長が伸びること(軸性近視)で起こります。定期的に眼軸長を測定することで、近視がどのくらいのスピードで進行しているのかを客観的に評価でき、治療効果の判定にも役立ちます。
- 眼圧検査・眼底検査など:緑内障など、他の目の病気がないかをチェックします。
これらの精密検査を通して、視力低下の本当の原因を突き止め、一人ひとりのお子さんに合った最適な対策や治療方針を立てることができるのです。
視力低下への対策と治療法|メガネをかけるだけじゃない選択肢
眼科での精密検査の結果、治療が必要と判断された場合、どのような選択肢があるのでしょうか。生活習慣の見直しから、最新の近視進行抑制治療まで、様々なアプローチがあります。
1. すぐに始められる!生活習慣の改善
視力の維持、そして近視の進行を緩やかにするためには、日々の生活習慣を見直すことが基本となります。今日からご家庭で取り組めることをご紹介します。
- 正しい姿勢と距離を保つ:本やスマートフォンを見るときは、目から30cm以上離しましょう。背筋を伸ばし、寝転がって本を読んだり、暗い場所でスマホを見たりするのはやめましょう。
- 部屋を明るくする:勉強や読書をする際は、部屋全体を明るくし、さらに手元を照らすデスクライトなどを併用するのが理想です。
- 休憩をこまめにとる:「20-20-20ルール」を意識してみましょう。これは、20分間近くを見たら、20フィート(約6m)以上遠くを20秒間眺めるというものです。タイマーをセットするなどして、意識的に目を休ませる習慣をつけましょう。
- 屋外で遊ぶ時間を増やす:近視進行抑制効果が報告されている太陽光を浴びるためにも、1日1~2時間程度、外で遊ぶ時間を作ることが推奨されています。習い事などで忙しいかもしれませんが、意識して屋外活動を取り入れましょう。
2. 適切なメガネによる視力矯正
「メガネをかけると、もっと目が悪くなるのでは?」と心配される保護者の方がいらっしゃいますが、これは誤解です。見えにくい状態を我慢している方が、かえって目に負担をかけ、肩こりや頭痛、学力低下につながることもあります。眼科で処方された、度数の合ったメガネを適切なタイミングで装用することは、快適な生活を送るために非常に重要です。
お子さんの場合、成長に伴って度数が変化しやすいため、定期的に眼科で検査を受け、常に適切な度数のメガネを使用することが大切です。
3. 近視の進行を抑えるための専門的な治療
近年、単に視力を矯正するだけでなく、近視の進行そのものを抑制するための治療法が確立され、注目されています。これらの治療は、お子さんの将来の目の健康を守る上で、非常に有効な選択肢となります。大阪鶴見まつやま眼科では、これらの近視進行抑制治療に積極的に取り組んでいます。
① 低濃度アトロピン(リジュセアミニ・マイオピン)点眼治療
「リジュセアミニ」「マイオピン」は、近視の進行を抑制する効果が科学的に認められている目薬です。低濃度(0.01%や0.025%)のアトロピンを1日1回就寝前に点眼するだけの、非常に簡単な治療です。眼軸長の伸びを抑えることで、近視の進行を平均で約60%抑制する効果が報告されています。副作用が非常に少なく、小さなお子さんでも始めやすいのが特徴です。
② オルソケラトロジー
「オルソケラトロジー」とは、夜寝ている間に特殊なデザインのハードコンタクトレンズを装用し、角膜の形状を一時的に矯正することで、日中を裸眼で快適に過ごせるようにする治療法です。角膜の形状を変化させることが、近視進行を抑制する効果もあることがわかっています。日中にスポーツを活発にするお子さんや、メガネやコンタクトレンズの煩わしさから解放されたい方に適しています。
③ 多焦点ソフトコンタクトレンズ
主に大人の老眼治療に使われる遠近両用のコンタクトレンズですが、その特殊なレンズ設計が、子供の近視進行を抑制する効果があることが分かってきました。日中に装用する使い捨てタイプのレンズもあり、オルソケラトロジーが適応でないお子さんにも選択肢となります。
これらの治療法は、それぞれにメリット・デメリット、適応となる年齢や近視の度数があります。どの治療が最適かは、眼科専門医がお子さんの目の状態やライフスタイルを総合的に判断して決定します。
大阪市鶴見区で子供の視力相談なら「大阪鶴見まつやま眼科」へ
ここまで読んでいただき、学校検診をきっかけとした眼科受診の重要性や、様々な治療の選択肢があることをご理解いただけたかと思います。
「では、どこの眼科に相談すればいいの?」
そうお考えの大阪市鶴見区、城東区、都島区、旭区、東大阪市、守口市、門真市、大東市など、周辺地域にお住まいの皆さまへ。お子さんの大切な目の相談は、「大阪鶴見まつやま眼科」にぜひお任せください。
なぜ「大阪鶴見まつやま眼科」が選ばれるのか
当院が、お子さんの視力低下の相談先として選ばれるのには理由があります。
1. お子さんの検査・治療経験が豊富です
院長をはじめスタッフ一同、お子さんが安心して検査や診察を受けられるよう、丁寧で優しい対応を心がけています。保護者の方にも、検査結果や治療方針について、専門用語をなるべく使わず、分かりやすくご説明することをお約束します。お子さんの不安、保護者の方の疑問、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
2. 正確な診断のための検査機器が充実しています
お子さんの正確な屈折度数を測るための調節麻痺薬を用いた検査はもちろん、近視の進行度を客観的に評価するための「眼軸長測定装置」など、診断に必要な専門的な検査機器を完備しています。これにより、一人ひとりのお子さんの目の状態を的確に把握し、最適な治療方針をご提案することが可能です。
3. 近視進行抑制治療に力を入れています
当院では、お子さんの将来を見据え、近視の進行を抑制するための治療に力を入れています。ご紹介した「低濃度アトロピン(マイオピン)点眼治療」や「オルソケラトロジー」など、複数の選択肢の中から、お子さんの目の状態やライフスタイルに最も合った治療法をご提案します。治療のメリットだけでなく、デメリットや費用についてもきちんとご説明し、ご納得いただいた上で治療を開始しますのでご安心ください。
4. アクセスが便利です
大阪鶴見まつやま眼科は、イオンモール鶴見緑地のすぐ近く、Osaka Metro長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅から徒歩圏内にあり、近隣にお住まいの方はもちろん、お買い物のついでにも立ち寄りやすい便利な立地です。駐車場もございますので、お車でのご来院も便利です。
【大阪鶴見まつやま眼科 】
〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目5-15
お電話でのご予約・お問い合わせ: [ここに電話番号を記載]
ウェブサイトからのご予約も可能です: [ここにウェブサイトURLを記載]
まとめ:お子さんの未来のために、最初のステップを
学校検診での視力低下の指摘は、決して不安になるためだけのものではありません。それは、お子さんの目の健康と向き合い、適切なケアを始めるための「大切なきっかけ」です。
「まだ見えるから大丈夫」「様子を見てから」という判断が、治療のタイミングを逃してしまうこともあります。特に、視力が大きく発達し、近視が進行しやすい学童期においては、早期の専門的な対応が、お子さんの生涯の「見え方」を左右すると言っても過言ではありません。
学校から「眼科受診のおすすめ」の紙をもらってきたら、それはお子さんの目からの大切なメッセージです。ぜひ、そのメッセージを受け止めて、眼科への一歩を踏み出してください。
大阪鶴見まつやま眼科は、大切なお子さんの目の健康を守るため、保護者の皆さまと一緒に、真摯に向き合ってまいります。どうぞ、安心してご相談ください。